お役立ち情報
簡単なレポート・論文の書き方

最近では、大学入試に論文があるケースも多くなりましたし、SNSやブログなどで文章を書くことも日常的にあると思います。
しかし、大学のレポートや論文は、専門用語も多く、長文で難解、読みにくいものが多いです。
しかも、過去の研究とのつながりが重視されるため、まったくの自己流というのでは、評価されません。
ここでは、簡単なレポートの書き方として、3つの構成を紹介します。
簡単なレポートの書き方3つの構成
レポートや論文には、書き方のコツがあります。それは、書き出す前に、まず全体の構成をすることです。
最近では、ユーチューバーが流行っていますが、動画を撮る前に、まずは構成を決めますよね。レポートや論文もこれと同じです。だいたいの構成を決めてから、詳細を書いていきます。
簡単な構成のパターンとして、次の3つを紹介します。
- 問題提起+根拠+意見
- 既存の議論+新しい議論+検討
- 理論+事例+検証
問題提起+根拠+意見

法学の基礎的なレベルのレポートでよくある書き方です。
① 最初に、テーマについてどのような問題点があるか述べます(問題提起)。
② 前提となる学説や法律の趣旨を述べます(根拠)。
③ 最後に、②の根拠に基づいて、①の問題点について自分の意見を述べます。
たとえば、「普通地方公共団体の条例制定権について」というテーマでレポートが出されたとします。上記の書き方に沿って、次のように構成します。
① まず、「条例制定権の及ぶ範囲」について議論が分かれている、という問題提起をおこないます。
② 次に、憲法において条例制定権を保障する根拠についての学説を述べます。確認規定説と創設規定説がありますので、これらの内容を書きます。
③ 最後に、②の学説のどちらの立場を採るかを明確にしたうえで、自分の意見を述べます。たとえば、創設規定説を採るなら、憲法94条の「法律の範囲内で」の解釈論によって方向性が決まるのではないか、という全体をまとめられるような視点から意見を述べます。
このように構成すると、良いレポートになるでしょう。
既存の議論+新しい議論+検討

レポートに限らず、論文などの長文で利用できる書き方です。
① まず、既存の議論を整理します。(既存の議論の前に、問題提起を置いた方がより良いですが、ケースバイケースです)
② ①を踏まえたうえで、①の議論に問題が生じ(問題提起をここで押さえます)、新しい議論が起こっていることを述べます。
③ ②の新しい議論について、自分の立場をはっきりさせて検討します。(この際、①とのつながりを意識します。特に法学の場合は、既存の議論との連続性が重視されるため、新しい議論の根拠となるものが乏しい場合は、外国の議論などを参照して補強します)
たとえば、「所得税法の給与所得該当性について」の修士論文を執筆するとします。上記の書き方に沿うと、次のように構成していきます。
① 所得税法における給与所得の意義について、所得税法における所得分類の趣旨・経緯、過去の税制調査会の議論、通説や代表的判例を整理します(既存の議論)。
② 近年、給与所得該当性について、従属性よりも非独立性を重視する議論が起こっていることについて、これらの立場を採る判例や学説を紹介します(新しい議論)。
法学の場合、「新しい議論」はたいてい、新しい解釈論を展開する判例から生じることが多いため、特定の判例を軸に、②の部分から論文を組み立てることが非常に有効です。
③ ②の議論を、①とのつながりを意識して、現代の労働者の実態、労働法における議論、外国法の参照などから検討し、自分の意見を述べます。
いかがでしょうか。
①、②、③という構成のくくりは、かなり大まかな部分であることがわかると思います。
それぞれのくくりの中で、論点が分かれるようでしたら、章を分けるなどしていくことになります。
このように、長いダラダラとした論文の中にも、はっきりとした論理の流れがあることを意識すると、途端に書きやすくなりますよ。
理論+事例+検証

法学では、当てはめなどと言って判例評釈などでよく見られます。社会学や文化人類学、文学などいわゆる文系一般のレポートでは有効な構成です。
① まず、理論を述べます。レポートや論文を書く際の方法論です。
② 理論を当てはめられるような事例を紹介します。理論は、複数の事例に共通して当てはまるような要素を定式化したものなので、それが正しいかどうか、検証できるような事例を探してくるわけです。この事例は、元々の理論を形成したときの事例と同様のものでは意味がなく、共通するところはあるけれども微妙に異なるような事例を用いる必要があります。事例とは、社会学や文化人類学であればフィールドワークであり、文学であれば小説や映画などであり、法学であれば判例になります。
③ ②の事例において、①の理論が当てはまるかどうかを検証します。
実績豊富な当ラボに相談ください
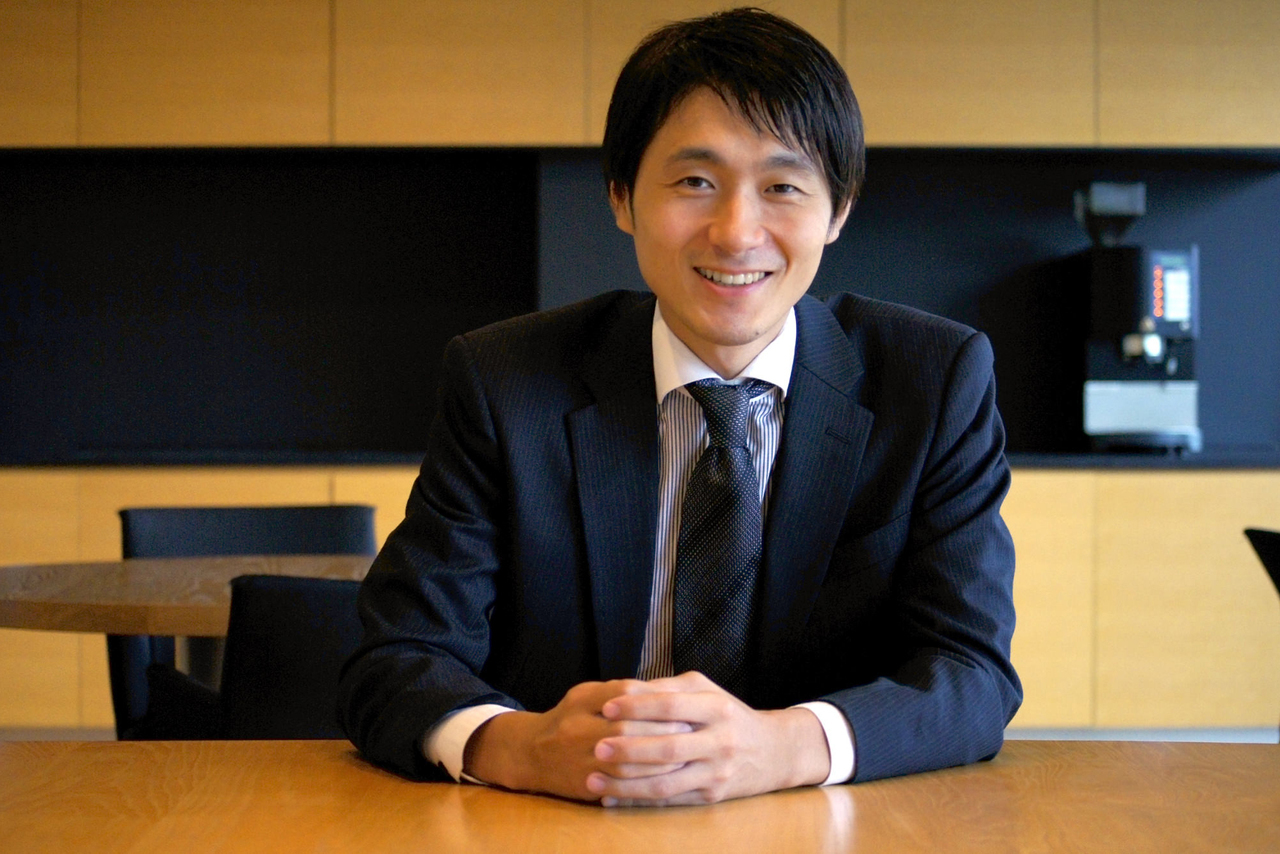
レポート・論文のお悩みを解決します!
当ラボでは、ここでご紹介したようなレポート・論文の構成を起案するサービスも承っています。
ある程度学力があり、自分で調べて考えることができる方であれば、レポート・論文の構成のアドバイスを受けるだけで飛躍的に書きやすくなります。
ご自分で書かれたレポート・論文を構成面から添削することも可能です。
その他、レポート・論文の骨子を作成することも可能です。
ごあいさつ

きめ細やかで誠実な対応を心掛けておりますのでお気軽にご相談ください。


